八海山がニューヨークからSAKEを輸入開始
新潟を代表する銘酒「八海山」で知られる八海醸造株式会社(南魚沼市)は、業務資本提携するニューヨークの酒蔵ブルックリンクラのSAKEを4月から日本で販売を開始します。また、自社で製造する主原料に米を使ったウイスキーをバーシーンに投入します。
ニューヨーク生まれのSAKEの輸入と米で造ったウイスキーのリリースを発表
「『永遠に終わらない会社』をテーマに掲げ、常に挑戦し進化してきた。希少性から脱しておいしいお酒を日常的に提供できるようにしたり、地元の魚沼の観光振興に取り組み年間30万人にお越しいただけるようにしたりしてきたのはひとつの例だ。
ニューヨークでSAKEを造るブルックリンクラと出会い、かねてから考えていた『日本酒を世界酒に』するためには、彼らと一緒に進むべきだと判断し2021年に業務資本提携を結んだ。日本人ではなく現地の人が地元の水や米でSAKEを造ることが世界酒になるためには重要だからだ。
また、ウイスキー造りに取り組み始めたのはずいぶん前だが、ようやく米で造ったグレーンウイスキーをリリースできた。これからも常に革新できる八海醸造グループを目指す」



ニューヨーク発の酒蔵ブルックリンクラとは?
当時のブルックリンクラの酒はまったく洗練されていなかったはずです。酒造りの経験も知見も乏しく十分な設備もなかったうえに、海外でのSAKE造りにはさまざまな制約があるからです。日本では酒造り用の米を容易に入手できますが海外にはありませんし、家庭用の精米機しかないので、米の外側を1割ほど削るのが精いっぱいです。おいしい酒を造るために日本で開発されたさまざまな素材や道具の多くを利用できません。
八海醸造との業務資本提携はこれらの制約のいくつかをなくしました。2023年にブルックリンクラは新しい醸造所を造りましたが、八海醸造から醪(もろみ)の搾り機(どろどろの発酵醪を酒と粕に分離する機械)やパストライザー(加熱殺菌した酒を急冷する装置)などを譲り受け、稼働させたのです。加えて技術的なアドバイスによって酒質が格段に上がったことは疑いありません。
そのほか新しい醸造所には小学校の教室ほどのセミナールームが設けられ、レストランやバーなどプロフェッショナル向けから一般の愛好家向けのカリキュラムが提供されます。講師は酒サムライのティモシー・サリバン氏です。
アメリカでのSAKE普及事情
2000年ごろからプレミアムSAKEとしてフルーティーな吟醸酒を冷やして楽しむスタイルがアメリカに登場します。この頃からレストランシーンではフレンチやイタリアンなど国際的な西洋料理が和食の影響を受け、生魚を使ったり、素材の味わいを生かす調理法を採用したりしたフュージョンといわれる業態が注目されて行くのですが、プレミアムSAKEはフュージョンレストランで提供されるようになります。

八海醸造から本格的シングルグレーン・ライスウイスキー登場
そんななか八海醸造は辛抱強くウイスキーの熟成を待ち、今年初めて商品化に踏み切りました。「Hakkaisan シングルグレーン 魚沼8年 ライスウイスキー2025LIMITED」です。特徴は何といっても原料の7割に米を使っている点です。モルトと米で造るウイスキーは、米と水と発酵にこだわり続けた八海醸造のプライドをかけた商品とも言えるでしょう。初リリースのこの商品は製造数量が少ないこともあり、バー向けに限定して販売されます。



※記事の情報は2025年4月3日時点のものです。
『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。
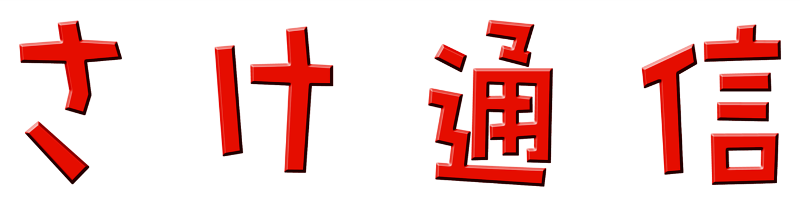
- 1現在のページ
 山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)
山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)